Blog 最新記事
カテゴリ
「コンプライアンス意識の欠如」を招く心理メカニズム
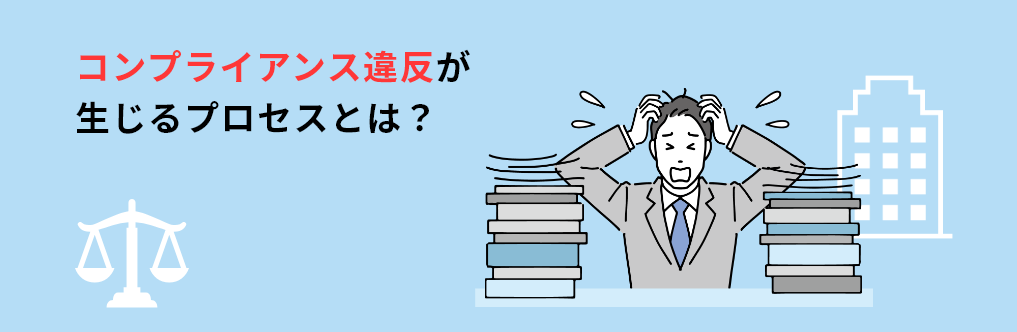
第1段階:現状維持を優先し、リスクの兆候を見逃す
最初の段階では、問題が生じる兆候があるにもかかわらず、組織がそれを軽視することが多く見られます。この背後には、現状維持バイアスと正常性バイアスが働いていることが多いです。
現状維持バイアスとは、現在の状態を変えることを避け、変化を嫌う心理傾向のことです。このバイアスが強く作用すると、組織は多少のリスクが見えても「今のやり方をわざわざ変える必要はない」と判断し、問題への対処をためらいがちです。
一方で、正常性バイアスも問題の早期対策を阻害します。正常性バイアスとは、危険が迫っていても「これまでは大きな問題がなかったから、今後も大丈夫だろう」と楽観的に考え、リスクを過小評価してしまう心理です。この心理により、組織は「多少の問題なら放っておいても大きな問題にはならない」と考え、リスクを積極的に捉えようとしません。
現状維持バイアスと正常性バイアス
例えば、製造業の現場で小さな品質不良が発見された場合を考えてみましょう。現場のスタッフや管理者は「大きな問題にはならない」として、対策を講じずに放置することがしばしばあります。このとき現状維持バイアスが強く働き、「製造プロセスを変えるのは面倒だから現状で大丈夫だろう」と考え、対応を先送りにしてしまいます。また、正常性バイアスが加わることで、「この程度なら深刻な問題にはならない」と楽観視し、事態を軽視してしまうのです。
結果として、こうした初期の小さなリスクが拡大し、やがてコンプライアンス違反やリコール、さらには大規模なクレームに発展することもあります。「問題を先送りにする」という選択が、後の大きな問題の原因を作り出しているのです。
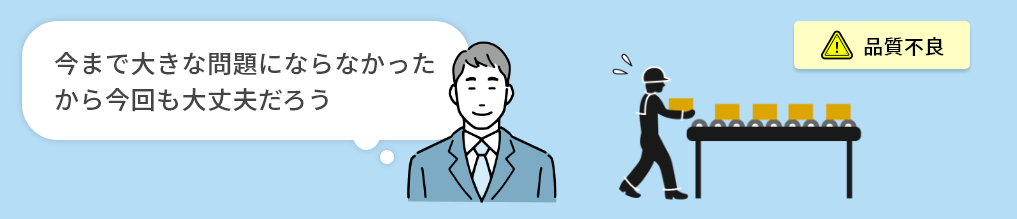
第2段階:損失回避の心理が焦りを生み、無理な行動に出る
次の段階に進むと、リスクが無視できないレベルで顕在化し、組織は「今すぐ何とかしなければならない」という強い焦りに駆られます。この段階で作用するのが、サンクコスト効果とリスク選好です。
サンクコスト効果とは、すでに投じた時間や資金、労力が無駄になることを避けようとする心理です。この効果によって、「これまでの投資を無駄にしたくない」という思いが強くなり、冷静な判断が難しくなります。組織は、損失を避けたい一心で無理をしてでも現在の状況を取り戻そうとするのです。
一方、リスク選好は損失を回避しようとするあまり、通常は避けるべきリスクを積極的に取ってしまう心理です。リスク選好が高まると、組織は「多少のリスクを取ってでも損失を取り戻したい」と考え、結果としてコンプライアンスを無視する判断に傾くことが多くなります。
サンクコストとリスク選好
例えば、ITプロジェクトが納期遅延に陥り、計画よりも多くの資金がすでに投入されている状況を考えてみましょう。経営陣やプロジェクトチームにはサンクコスト効果が働き、「今までの投資が無駄になるわけにはいかない」として、多少の無理をしてでもプロジェクトを完了させようとします。この焦りから、リスク選好の心理も作用し、「多少の規制違反があっても今は仕方がない」として、テスト工程を簡略化してしまうことがあります。
短期的な目標達成を優先してしまい、コンプライアンス違反につながる行動が選ばれやすくなるのです。

第3段階:倫理観を失い、「非常手段」に訴える
最終段階では、組織全体が「何が何でもやらなければならない」という危機的な心理状態に追い込まれます。この段階で働くのが道徳的離脱と集団浅慮です。
道徳的離脱とは、通常は倫理的に許されない行為も「今はやむを得ない」として自らを正当化する心理です。道徳的離脱が起こると、組織は「生き残るためならばコンプライアンス違反も仕方ない」という認識に変わり、普段は考えられない違反行為に手を出してしまいます。
また、集団浅慮の影響により、組織全体が結束を重視しすぎて異なる意見を排除する傾向が強まります。これにより、「皆が同じ方向を向いているから問題はないだろう」として、批判的な意見が抑えられ、問題に対する冷静な検討が行われなくなります。
道徳的離脱と集団浅慮
ある企業が業績の悪化に直面し、赤字を隠すために利益を操作するケースを考えてみましょう。普段なら不正な会計操作は厳しく禁じられていますが、道徳的離脱が働くと、「生き残るためだからやむを得ない」と考え、不正な利益操作が正当化されてしまいます。さらに、経営陣が集団浅慮に陥り、他のメンバーも「これが組織のためだ」として異論を挟まない状態に陥ることで、不正行為が見逃され、違反行為が常態化してしまうのです。このようにして、コンプライアンス違反が組織全体に広がり、重大な問題として発覚するリスクが高まります。

コンプライアンスを守るために必要なこと
これらの心理的なバイアスに対応するためには、組織が冷静に判断を下せる体制を整えることが重要です。リスクの兆候が現れたときには、現状維持バイアスや正常性バイアスに気づき、問題を先延ばしにしないための仕組みを持つことが不可欠です。例えば、品質管理プロセスの見直しや、早期警告システムを導入し、リスクを検出した際には迅速に対応する体制を築くことが効果的です。
また、組織が焦って無謀な行動に走らないためには、サンクコストに囚われずに冷静にリスクを評価する文化が必要です。コンプライアンス教育やリスク管理トレーニングを通じて、判断力を日頃から高めておくことで、危機的な状況にあっても冷静な対応が可能になります。
さらに、道徳的離脱や集団浅慮を避けるために、組織内で意見を交わしやすい環境を整え、多様な意見を受け入れる文化を育むことが求められます。リスクが顕在化した際には、透明性のある議論を行い、従業員が疑問や懸念を率直に表明できる環境を整えることが大切です。これにより、組織が誤った方向に流れることを防ぎ、コンプライアンスを強化する土台が築かれます。
弁護士によるコンプライアンス対策セミナー
コンプライアンスが重視されているにも関わらず、コンプライアンス違反はなかなか後を絶ちません。
「なぜ、これぐらいならいいだろうと思ってしまうのか」「やめておこうと言い出せない空気の正体は何だ」といった心理学観点から、コンプライアンス対策について解説する「コンプライアンス対策セミナー」を開いています。
詳しくは、「企業研修・セミナー」をご覧ください。






コンプライアンス(法令遵守)は、信頼を築き、持続的な成長を目指す企業にとって欠かせない基盤です。
しかし、いざ問題が発生したとき、組織は冷静さを欠き、結果としてコンプライアンス違反に陥ることが少なくありません。これは「ミス」だけではなく、組織全体に無意識に働く心理的なメカニズムが大きく影響しています。ここでは、コンプライアンス違反が生じやすいプロセスについて、具体例を交えながら3つの段階に分けて説明します。