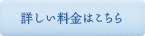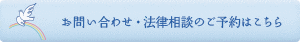Blog 最新記事
- 「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性〔後編〕(COACHING times)2025-07-03
- 「良かれと思って」に潜むハラスメントの可能性〔前編〕(COACHING times)2025-07-02
- 著者インタビューを掲載頂きました2025-06-25
- 経営戦略で幸せな人生をプロデュースする―『人生の経営戦略―自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20』から学ぶ実践知―2025-06-18
- 不動産分野のメディア・コラムなど2025-06-10
カテゴリ
債権回収の問題が起こってしまう理由とは?
今回からインタビュー形式で、法律に関する皆様の素朴な疑問にお答えする記事を発信していきます。
目次
相手の会社が倒産状態で、社長も一文無しになっている場合の債権回収って可能なの?
非常に難しいケースですね。オフィスに行っても誰もいない。社長の居場所もわからないし、連絡をとれない。こうした状況での債権回収は、「私ども(弁護士)が動けば動くほど、赤字が増えるかもしれません」としっかりお伝えした上でご依頼を受けることがあります。ただ、非常に難しいケースとはいっても、全くの無意味という訳ではありません。
例えば、今すぐには回収の見込みが立たなくても”時効の中断”という時効消滅を食い止める手続きを行っておくことは大切です。なぜなら、何も手続きをしないと債権は1年~5年あるいは10年で消滅してしまいます。しかし、判決を得ていれば更に10年間時効を延ばすことができます。つまり、「今」の時点で債権回収ができなくても、「10年後」に債権を回収できるかもしれないということです。会社が持ち直しているかもしれないし、あるいは社長が別の事業で再起しているかもしれない。そうした事例は沢山あります。長い目で機会をうかがうのも一つの手です。
債務者がお金を払えるにも関わらず、債権回収の問題が起きることはある?
もちろん、あります。ただ、発注をしておきながら支払う気がそもそもないという経営者はそれほど多くありません。実際、債権回収の問題は言葉や感覚の行き違いによって起こることがほとんどです。
たとえば、機械の取引の場合に、納めた側は十分動くものを納めたので、取引を果たしたと思っていても、顧客の側が、実はそれ以上の性能を求めていたという場合です。商品を納めたから代金が欲しいという主張と、言ったとおりのものが納められていないという主張がぶつかってしまいます。
また別のケースもあります。内装工事で壁を白く塗ったとします。業者としては、言われた通り白く塗ったから代金が欲しいところですが、「白は、もっと別の白のことを言っていた」と主張されてしまい、たちまち債権回収の問題に発展してしまうのです。
ご紹介した2つのケースは、どちらが悪いという話ではなく、納品物の定義の行き違いによって起こってしまった問題です。
このような行き違いを事前に防ぐために、契約書が存在します。
契約書がない場合に債権を回収することは難しい?
もちろんあるに越したことはありませんが、契約書がないからといって、取引もなかったことにするというような無茶苦茶はできません。納品書など支払う側のハンコが入った書類や、メールのやり取りでも 十分な証拠になり得ます。要注意なのは、請求書だけでは証拠としては不十分なことです。なぜなら請求書は、「この金額でお願いします」ということを相手に伝える書類にすぎないからです。
十分な証拠になり得ます。要注意なのは、請求書だけでは証拠としては不十分なことです。なぜなら請求書は、「この金額でお願いします」ということを相手に伝える書類にすぎないからです。
最後に
何気なく使っている言葉の意味は、人それぞれで自然と違ってきてしまいます。「言った・言わない」の水かけ論になってしまうと、手間がかかる以上に、相手との関係が壊れてしまいます。債権回収問題を防ぐ意味でも、契約書はできるだけ事前に交わすようにしておきたいものです。債権回収についてお悩みでしたら、波戸岡にお気軽にご相談頂ければと思います。
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。
そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。
私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。
また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。
経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。
そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。

波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
著書紹介
『論破されずに話をうまくまとめる技術』
”論破”という言葉をよく聞く昨今。
相手を言い負かしたり、言い負かされたり、、、
でも本当に大切なことは、自分も相手も納得する結論にたどりつくこと。
そんな思いから、先人たちの知見や現場で培ったノウハウをふんだんに盛り込み、分かりやすい言葉で解説しました。
『ハラスメント防止と社内コミュニケーション』
ハラスメントが起きてしまう背景には、多くの場合、「コミュニケーションの問題」があります。
本書は、企業の顧問弁護士として数多くのハラスメントの問題に向き合う著者が、ハラスメントを防ぐための考え方や具体的なコミュニケーション技術、実際の職場での対応方法について、紹介しています。
『弁護士業務の視点が変わる!実践ケースでわかる依頼者との対話42例 コーチングの基本と対応スキル』
経営者が自分の判断に自信をもち、納得して前に進んでいくためには、経営者に伴走する弁護士が、本音で対話できるパートナーであってほしいです。
本書では、経営者に寄り添う弁護士が身につけるべきコミュニケーションのヒントを数多く解説しています。
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
東京都港区赤坂3-9-18赤坂見附KITAYAMAビル3階
TEL 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674